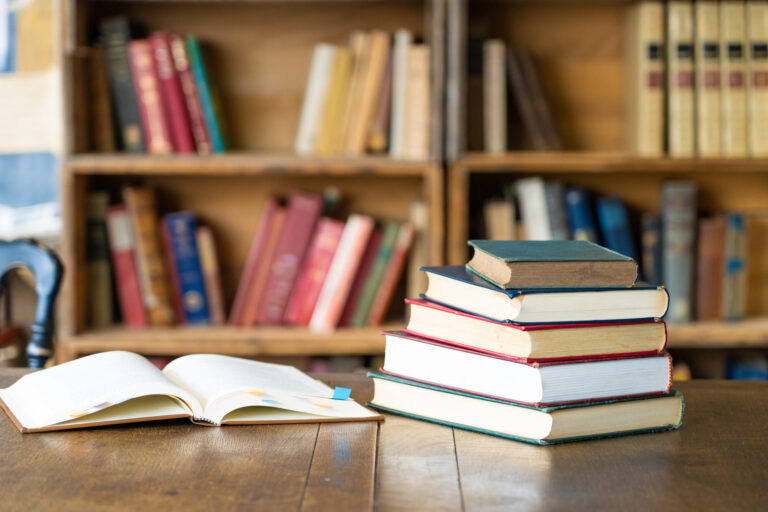M&Aは、企業の成長戦略において重要な役割を果たす手法です。
しかし、M&Aを成功させるには法務、財務、税務などの専門知識が不可欠で、そのための資格を取得することが大きなメリットとなります。
この記事では、M&Aに関連する国家資格と民間資格の種類、難易度、取得にかかる費用を解説し、どの資格がキャリアに役立つかを明らかにします。
- この記事を監修した人:福住優(M&A情報館 代表取締役)
M&Aに必要な資格とは?
M&Aは、企業が他の企業を統合したり、買収したりする取引を指します。
このプロセスには、財務、法務、税務、戦略など、幅広い分野の専門知識が必要とされます。そのため、多くの人が「M&Aを行うには特定の資格が必要なのでは?」と思うかもしれません。しかし、実際のところ、M&A業務を行うために必須の資格は存在しません。
とはいえ、M&A取引を成功させるには高度な専門知識が求められるため、関連する資格を保有することで得られるメリットは非常に大きいです。
資格を持っていることで、顧客や取引先に対して自分の専門性をアピールすることができ、信頼感を高める効果が期待できます。
また、複雑なM&Aのプロセスでは、法的な契約や税務上の調整、企業価値の算定など、多岐にわたる知識を総合的に活用する必要があります。
これらのスキルを効率的に身につけるために、資格取得は有用な手段となるのです。
M&A業務に携わる人々は、財務や法務、税務の分野での資格を取得することで、業務の信頼性と自信を高めることができるだけでなく、実務に必要な知識とスキルを強化できます。
例えば、公認会計士や税理士、弁護士などの資格を持つ専門家は、M&Aのプロセスで特に重要な役割を担います。また、民間資格としてM&Aの実務に特化した「M&Aスペシャリスト資格」や「JMAA認定M&Aアドバイザー」といった資格もあり、これらを取得することでM&A分野での専門知識を証明することができます。
さらに、近年、中小企業庁が設定しているM&Aガイドラインにおいても、M&Aアドバイザーや仲介業者が保有している資格を明示することが求められる可能性があるとされています。
このような動きは、資格保有者の専門性を強調することで、取引の透明性を確保し、クライアントが安心してM&A業務を依頼できる環境を整えるためのものです。
したがって、今後M&Aの支援を行うにあたっては、資格の有無がより一層重要視される可能性があります。
このように、資格が必須ではない一方で、M&Aの成功に向けて必要な専門知識やスキルを効率的に習得するため、そして顧客からの信頼を得るために、資格の取得は非常に大きなメリットがあります。
特に、弁護士、公認会計士、税理士などの国家資格や、M&Aに特化した民間資格を取得することで、業務の幅が広がり、より専門的な役割を担うことができるようになります。
今後M&Aに携わることを考えている人は、自分に合った資格を取得することを検討してみると良いでしょう。
M&A資格取得のメリット
M&Aに関連する資格を取得することには、実務におけるさまざまな利点があります。
M&A業務は非常に専門的な知識を要する分野であり、法務、財務、税務、経営戦略など、幅広いスキルが必要です。そのため、これらの知識を体系的に学ぶことができる資格を取得することで、業務の質を高めることができます。
また、資格を持っていることで、自身の専門性を証明できるため、顧客やビジネスパートナーからの信頼を得やすくなるのも大きなメリットです。
加えて、M&A資格を保有することで、キャリアアップや収入向上のチャンスも広がります。
ここでは、具体的にM&A資格取得のメリットについて見ていきましょう。
専門知識の習得と信頼性の向上
M&Aの資格取得は、専門知識を体系的に習得するための有効な手段です。
M&Aは企業の売買や統合といった重要なビジネス戦略の一環であり、そのプロセスには法的手続きや税務処理、企業価値の評価など、多くの複雑な要素が絡んでいます。
これらの業務を正確かつ効率的に進めるには、深い専門知識が必要不可欠です。資格を取得することで、こうした知識をしっかりと身につけることができるため、M&Aの実務において大きなアドバンテージとなります。
また、資格はその人が一定の専門的な知識を持っていることを証明するものです。M&A業務を進める際、顧客やビジネスパートナーは「この人に任せて大丈夫か?」という点を重要視します。
資格を持っていることで、顧客やパートナーに対して自分のスキルや知識をアピールでき、信頼を得やすくなります。特に、弁護士や公認会計士、税理士といった国家資格は社会的な信頼性も高く、これらの資格を持つことによって、M&Aのプロフェッショナルとしての地位が確立されるでしょう。
これにより、重要な取引や案件を任される機会も増えるため、業務の幅が広がると同時に、自身のキャリア形成にもプラスに働きます。
キャリアアップと収入向上の可能性
M&Aに関連する資格を取得することは、キャリアアップや収入向上の大きなきっかけとなります。
特に、M&A業務は高い専門性が求められるため、その分、報酬も比較的高い傾向にあります。資格を取得することで、M&Aアドバイザーやコンサルタントとしての専門性をアピールできるため、これまで以上に高い役職に就くチャンスが生まれます。
また、資格保有者は転職市場でも有利に働くことが多く、M&A業務を専門とするコンサルティング会社や金融機関、法律事務所、会計事務所など、さまざまな分野での就職・転職の選択肢が広がります。
資格を持っていることによって、自分のキャリアの幅を広げることができるのも大きなメリットです。たとえば、M&Aスペシャリスト資格やJMAA認定M&Aアドバイザーなど、特定の分野に特化した民間資格を取得しておくと、M&A実務の専門家としてより深く業務に携わることができます。
また、公認会計士や弁護士などの国家資格を持っている場合には、M&Aにおけるデューデリジェンスや契約書の作成、企業価値の評価など、より専門的な業務を担うことができるようになります。
M&Aに関するおすすめの国家資格7選
M&A業務は、財務、法務、税務、経営戦略など、さまざまな専門知識が求められる複雑な分野です。そのため、これらの知識をしっかりとカバーできる資格を持つことで、M&Aに携わる際の信頼性や専門性が高まります。
特に国家資格は、その専門分野において高度な知識とスキルを持つことを証明するものであり、M&Aのプロフェッショナルとしてキャリアアップするための強力な武器となります。ここでは、M&Aに関連するおすすめの国家資格7つについて解説します。
公認会計士
まずは、公認会計士の資格に関して簡単に解説していきましょう。
概要と試験内容
公認会計士は、企業の財務状況を評価し、正確な会計報告を行う専門家です。
M&Aにおいては、デューデリジェンス(買収対象企業の調査)や企業価値の算定、統合計画の策定といった重要な役割を担います。M&Aの成否は、買収対象企業の財務状況の正確な把握にかかっているため、公認会計士の専門知識が非常に重宝されます。
公認会計士試験は、「短答式試験」と「論文式試験」の2段階に分かれており、短答式では財務会計論や管理会計論、企業法などの基本知識が問われます。論文式では、さらに高度な知識を要する科目が含まれ、総合的な理解力が求められます。
M&A仲介手数料の費用相場やその計算方法について解説し、仲介会社を選ぶ際に注意すべきポイントを掘り下げます。また、近年の…
難易度と合格率
公認会計士試験は、国家資格の中でも特に難易度が高い試験です。試験範囲が広く、計算問題や論述問題が含まれるため、合格までには数年の勉強が必要とされる場合も多いです。合格率は10%前後と低めで、試験勉強にはかなりの時間と努力を要します。
受験費用
受験料は19,500円ですが、予備校や専門学校に通う場合の費用も考慮する必要があります。
税理士
次に税理士の資格について解説していきましょう。
概要と試験内容
税理士は、企業の税務に関する専門家で、M&Aにおいても税務戦略の立案や法人税の計算などで重要な役割を果たします。税務はM&Aのコストや取引後の企業の利益に直結するため、正確かつ効率的な税務処理が求められます。
税理士試験は、必修科目(簿記論、財務諸表論)、選択必修科目(法人税法、所得税法)および選択科目から合計5科目を合格する必要があります。科目ごとに合否が判定されるため、一度にすべての科目を合格しなくても段階的に進められるのが特徴です。
難易度と合格率
税理士試験は難易度が高く、特に法人税法や所得税法といった科目は難関とされています。試験合格までには数年かかることも多く、合格率は10%程度です。科目別に合格を目指せるため、少しずつ学習を進められますが、それでも総合的な知識が求められます。
受験費用
| 受験申込科目数 | 1科目 | 2科目 | 3科目 | 4科目 | 5科目 |
| 受験手数料 | 4,000 円 | 5,500 円 | 7,000 円 | 8,500 円 | 10,000 円 |
弁護士
M&Aにおいては、弁護士資格も有用です。以下では、弁護士資格について簡単に解説します。
概要と試験内容
弁護士は法的手続きや契約に関する専門家です。M&Aでは、基本合意書や最終契約書の作成、法律問題のリスク評価などを担当し、法的なトラブルを防ぐために不可欠な役割を担います。
弁護士になるためには、司法試験に合格する必要があり、試験は「短答式試験」と「論文式試験」の2段階で構成されています。法科大学院修了者または予備試験合格者のみが司法試験を受験できます。
難易度と合格率
司法試験は日本でも最難関の試験のひとつで、予備試験の合格者ですら高い難易度に苦しむことが多いです。合格率は20%前後ですが、実際に試験を通過するのは、十分な準備と深い理解が必要です。
受験費用
司法試験の受験料は28,000円です。また、法科大学院の学費や予備校の費用も考慮する必要があります。
司法書士
次に、司法書士について解説していきましょう。
概要と試験内容
司法書士は、不動産登記や商業登記に関する手続きを担当する専門家です。M&Aのプロセスでは、事業譲渡に伴う不動産の移転や、組織再編時の登記変更などで重要な役割を果たします。
試験は、択一式と記述式で構成され、登記法、民法、商法などの法律知識が問われます。受験資格に制限はなく、毎年多くの受験者が挑戦しています。
難易度と合格率
司法書士試験は合格率が4~5%と非常に低く、試験範囲が広いため、難易度の高い試験とされています。特に記述式の問題では、正確かつ迅速な解答が求められます。
受験費用
受験料は8,000円です。
中小企業診断士
さらに、中小企業診断士について解説していきましょう。
概要と試験内容
中小企業診断士は、企業の経営改善や成長戦略のサポートを行う専門家です。M&Aの場面では、企業の価値を最大化するための戦略的アドバイスを提供し、特に中小企業の事業承継や統合後の経営サポートを担います。
試験は「1次試験」と「2次試験(筆記・口述)」に分かれており、さらに合格後には実務補習・実務従事が必要です。これらをすべてクリアして、中小企業診断士として登録されます。
難易度と合格率
1次試験は合格率20%~40%ですが、2次試験の合格率は20%程度とやや低めです。ストレート合格は難しく、複数回に分けて合格を目指す人も多いです。
受験費用
1次試験13,000円、2次試験17,200円、実務補習には追加費用がかかります。
社会保険労務士
加えて、社会保険労務士について解説します。
概要と試験内容
社会保険労務士は、労働関連の法律や社会保険に精通している専門家です。M&Aでは、買収先の労働環境や雇用条件を精査し、人事・労務デューデリジェンスを担当することが多いです。
試験は、選択式と択一式で構成され、労働基準法や社会保険法といった知識が問われます。受験資格には、学歴や実務経験が求められます。
難易度と合格率
合格率は6~7%と非常に低く、科目数も多いため、十分な学習時間が必要です。
受験費用
受験料は15,000円です。
ファイナンシャルプランナー
最後に、ファイナンシャルプランナー資格について解説します。
概要と試験内容
ファイナンシャルプランナー(FP)は、財務に関する幅広い知識を持ち、企業や個人に対して資産運用や保険、税金に関するアドバイスを行います。M&Aでは、買収後の資金管理や財務戦略の立案に役立つ資格です。
FP資格には、国家資格(FP技能士)と民間資格(AFP、CFP)があり、FP技能士試験は1級、2級、3級と分かれています。試験は学科試験と実技試験で構成されています。
難易度と合格率
FP技能士の1級は合格率が10%程度と難関ですが、2級は25%程度、3級は70%と比較的取得しやすいです。
受験費用
1級の学科試験は8,900円、実技試験は20,000円~25,000円。2級・3級はそれぞれ異なる価格設定です。
M&Aに関連するおすすめの民間資格4選
M&A業務に携わるために役立つのは、国家資格だけではありません。M&Aに特化した民間資格も多くあり、これらの資格を取得することで、より専門的な知識を身につけることができます。
特にM&Aの実務に関するスキルや、事業承継に関する専門知識を証明できる資格は、M&A業界でのキャリアアップに大きな効果を発揮します。ここでは、M&Aに関連するおすすめの民間資格4つについて解説します。
M&Aスペシャリスト資格
まずは、M&Aスペシャリスト資格について解説します。
概要と試験内容
M&Aスペシャリスト資格は、一般社団法人日本経営管理協会が運営・認定する資格で、M&Aの知識に加えて実務で活用できるスキルを持つスペシャリストであることを証明するものです。この資格は、M&Aの現場で役立つ実務的な知識を学びたい方に特におすすめです。
M&Aの基礎から実務に至るまでの幅広い知識を網羅しており、M&Aに関する全体的な流れや手続き、デューデリジェンス、契約の作成といった具体的な業務に直結した内容を学ぶことができます。
資格取得には、支援講座を受講した後、検定試験を受ける必要があります。試験は選択問題と論述問題で構成されており、それぞれの合格基準をクリアすることで資格を取得できます。特に、実務経験のある講師が講義を行うため、現場での実践的なノウハウを学べるのが魅力です。
難易度と受験料
支援講座があるため、知識を効率的に学ぶことができますが、内容が広範囲であるため、難易度はやや高めです。試験自体も論述問題が含まれており、しっかりと理解していないと解答が難しい設問もあります。受講料は77,000円(税込)、検定試験料は11,000円(税込)で、総額88,000円(税込)となります。
資格取得のメリット
この資格を取得することで、M&Aの実務において必要な知識を一通り網羅でき、即戦力として活躍することが期待できます。
また、M&Aスペシャリスト資格は、企業間の連携や統合をスムーズに進めるための専門家としての信頼性を高めるためにも役立ちます。
資格取得後には、業界の第一線で活躍する講師から最新の情報を得るためのイベントも定期的に開催されており、継続的に学べる環境が整っているのも大きなメリットです。
JMAA認定M&Aアドバイザー
次に、JMAA認定M&Aアドバイザーについて解説していきましょう。
概要と試験内容
JMAA認定M&Aアドバイザーは、一般社団法人日本M&Aアドバイザー協会が運営している民間資格で、M&Aに関する専門知識を有するアドバイザーとしてのスキルを認定するものです。この資格を取得するためには、指定された講座を受講し、協会が定めた審査に合格する必要があります。
試験形式ではなく、講座の受講と実務に即した審査を通じて取得するため、実務経験が少ない方でも講座を通じてスキルを高めることが可能です。
難易度と受験料
試験形式がないため、一見すると取得しやすそうに感じますが、JMAAによる厳格な審査をクリアしなければならないため、一定の知識とスキルが求められます。
受講料は198,000円、入会金は33,000円、さらに月会費が年間132,000円(年間一括払い)と、取得にかかる費用は高めですが、資格を取得すると手厚いサポートが受けられるため、投資する価値は十分にあります。
資格取得のメリット
JMAA認定M&Aアドバイザー資格を取得することで、M&A業界において高い信頼性を持つアドバイザーとしての地位を確立することができます。
また、資格取得者は年に2回開催されるJMAA認定M&Aアドバイザー会員の集まりに参加できるため、業界のネットワークを広げるチャンスにもなります。
この会員の集まりでは最新の業界動向が共有され、参加者同士の交流を通じて、新たなビジネスチャンスを見つけることも可能です。
M&Aエキスパート認定資格
さらに、M&Aエキスパート認定資格について解説します。
概要と試験内容
M&Aエキスパート認定資格は、日本M&Aセンターと金融財団事情研究会が共同で企画・運営している資格です。
M&Aの基礎知識から応用まで幅広く学ぶことができるため、初心者から経験者まで、各レベルに合わせた試験が用意されています。
具体的には、「事業承継・M&Aエキスパート」「事業承継シニアエキスパート」「M&Aシニアエキスパート」といった段階的な資格があり、それぞれの段階に応じた試験があります。
難易度と受験料
「事業承継・M&Aエキスパート」はM&Aの基礎的な知識を対象としているため、比較的取得しやすい資格ですが、上位資格になると専用の養成スクールを修了しなければ試験を受けられないため、難易度が高くなります。受験料は7,700円で、他の資格に比べるとリーズナブルですが、上位資格を目指す場合には追加の費用や時間が必要です。
資格取得のメリット
M&Aエキスパート認定資格は、自分の知識レベルに応じて資格を選べるため、無理なくステップアップできるのが特徴です。
上位資格を取得すれば、M&Aの専門家として高度な知識を持つことを証明できるため、より複雑な案件に携われるようになります。また、資格取得者は継続的に学習できる環境が整っており、最新のM&A動向を学び続けることができます。
事業承継士
最後に、事業承継士について解説していきましょう。
概要と試験内容
事業承継士は、一般社団法人事業承継協会が運営・認定している資格で、特に事業承継に関連する知識を深めるための資格です。
M&Aだけでなく、親族内承継や従業員への承継といったシナリオに対応するための知識も学べるため、中小企業の経営者に対して幅広い提案が可能になります。
試験は選択問題と記述問題が組み合わされており、受験するためには中小企業診断士や税理士、弁護士などの資格を有していることが条件となります。
難易度と受験料
受験資格自体に難易度の高い資格が必要であるため、事業承継士になるためのハードルは高めです。
しかし、試験内容は基本的な知識を理解していれば合格しやすく、資格取得講座の受講後に試験を受ける形式となっています。講座費用は300,000円、認定試験料は9,000円、入会金は10,000円です。
資格取得のメリット
事業承継士の資格を取得すると、事業承継に関する専門知識を持つことが証明でき、中小企業の事業承継案件に携わる機会が増えます。
特に、事業承継センター株式会社から案件が優先的に紹介されるため、ビジネスチャンスが広がるのも大きなメリットです。また、協会を通じて最新の法律や税制についての情報を得られるため、常に知識をアップデートできる環境が整っています。
M&A資格取得に関する3つの注意点
M&Aに関する資格を取得することは、専門知識を習得し、業務における信頼性を高めるための効果的な方法です。しかし、資格取得にはいくつかの注意点もあり、それを理解した上で計画的に準備することが重要です。
ここでは、M&A資格取得における3つの注意点について解説します。
1. 資格によって求められるスキルが異なる
M&A業務は多岐にわたる分野の専門知識を必要としますが、資格ごとにカバーするスキルや得意分野は異なります。例えば、弁護士資格は法的な問題に強く、契約書の作成や法務デューデリジェンスといった法務全般をカバーするのに役立ちます。
一方、税理士資格は税務処理や税金対策に特化しており、M&Aにおける税務戦略の立案やコスト削減などで専門的なアドバイスを提供する際に重宝されます。また、公認会計士は財務に関する高度な知識を持ち、企業価値の算定や統合計画の策定など、財務分析において重要な役割を果たします。
そのため、M&Aの現場で求められるスキルや、自身が担当したい分野に応じて適切な資格を選ぶことが重要です。たとえば、経営戦略や事業の統合計画に興味がある場合、中小企業診断士やファイナンシャルプランナーの資格が有効です。
資格を取得する前に、自分のキャリアプランやM&Aにおける目指す専門分野を明確にしておくことで、最適な資格を選ぶことができ、スキルの習得に無駄がなくなります。
2. 国家資格は難易度が高い
M&A関連の国家資格(弁護士、公認会計士、税理士など)は、非常に難易度が高く、取得するまでに相当な時間と努力が必要です。
これらの資格試験は、法律や財務、税務に関する深い知識を問うものであり、試験範囲が広く複雑です。
そのため、合格率は低く、1回の受験で合格するのが難しい試験も多いです。
たとえば、公認会計士試験は合格率が約10%前後で、受験者は数年間にわたり専門学校で学びながら試験に挑むのが一般的です。税理士試験も科目ごとに分かれているため、複数年かけて合格を目指す人が多いです。
また、国家資格を取得するには、試験勉強だけでなく、専門学校や予備校での指導を受けることが推奨される場合もあります。
これらの学校では試験に向けた体系的な学習プランが提供されており、効率的に知識を深められますが、その分時間と費用もかかります。取得を目指す場合は、勉強時間の確保と学習計画をしっかり立てて、長期的な視点で準備を進めることが大切です。
3. 受講料や講座費用がかかる
資格取得には試験の受験料だけでなく、講座や予備校の費用、教材費などがかかる場合があります。特に民間資格の場合、取得を目指す際に指定の講座を受講する必要があり、その費用が高額になることも少なくありません。
たとえば、JMAA認定M&Aアドバイザーの講座受講料は198,000円、月会費も年間132,000円と、継続的に費用が発生するため、予算に余裕を持って計画する必要があります。
また、国家資格であっても、試験勉強にかかる教材費や専門学校の学費を考慮すると、かなりの出費になることがあります。公認会計士や税理士のような難関資格の場合、専門学校や通信教育を利用して勉強するのが一般的ですが、これらのコースには高額な費用がかかることが多いです。
そのため、資格を取得する前に、事前に必要なコストを調べ、予算を組むことが重要です。
M&A資格の中には、受講や受験の費用だけでなく、資格取得後に継続教育や更新のための費用が発生する場合もあります。
たとえば、弁護士や税理士は資格の維持にあたり、定期的な研修や教育が必要とされるため、それに伴う費用も視野に入れておくべきです。資格取得のためのコストを抑えるためには、オンライン講座を利用したり、独学で対応できる部分は積極的に学んだりする工夫も効果的です。
これら3つの注意点を踏まえ、M&A資格の取得を検討する際は、自分のキャリア目標とライフスタイルに合った資格を選び、計画的に準備を進めることが成功の鍵となります。
専門的な知識を深めることで、M&Aの実務における信頼性が向上し、さらに多くのビジネスチャンスを得ることができるでしょう。しかし、時間やコストがかかるため、しっかりとした計画と準備が必要です。
M&A資格取得のための学習方法
M&Aに関する資格を取得するためには、適切な学習方法を選び、計画的に準備を進めることが重要です。学習方法には、自己学習や専門学校・講座の利用、そしてオンライン学習などがあり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
自身のライフスタイルや学習スタイルに合わせて、最適な方法を選ぶことで、効率的に資格取得を目指すことができます。
ここでは、それぞれの学習方法について解説します。
自己学習
自己学習は、自分のペースで学びを進められるため、柔軟な学習スケジュールを組むことができる点が大きなメリットです。
特に、仕事や家庭の都合で決まった時間に学ぶことが難しい場合、自己学習は非常に有効な方法です。
また、自分に合った教材を選び、興味のある分野や苦手な部分に重点を置いて学習を進めることができるため、効率的に知識を習得できます。
自己学習の最大の魅力は、学習の自由度が高いことです。自分の理解のペースに合わせて勉強を進められるため、早く進めたい部分はどんどん学び、時間をかけて理解したい部分にはじっくりと時間を割くことができます。
教材選びも自由なので、最新の書籍やオンラインリソースを利用しながら学ぶことができるのも利点です。さらに、コストを抑えることができるため、専門学校や講座に通うよりも安く資格取得を目指せる点も魅力的です。
しかし、自己学習にはデメリットもあります。学習の進捗や理解度を自己判断しなければならず、モチベーションの維持が難しい場合があります。
また、M&Aに関する専門的な知識は難解な部分も多く、教材だけでは理解が難しいケースもあります。そのため、自己学習を選ぶ場合は、計画的に学習時間を確保し、理解しにくい部分については専門書や追加のリソースを利用するなどの工夫が必要です。
専門学校・講座の利用
専門学校や講座で学ぶ方法は、M&Aに関する知識を効果的に習得するための手段として非常に有効です。
専門学校では、実務経験豊富な講師から直接指導を受けることができ、教科書だけでは理解しにくい実践的な知識や具体的な事例を学ぶことができます。
講師がリアルタイムで質問に答えてくれるため、理解しにくい部分や疑問点をその場で解消できるのも大きな利点です。
また、講座に参加することで、同じ目標を持つ他の受講生と交流できる機会が得られます。受講生同士で情報を共有したり、お互いの学習進捗を励まし合ったりすることで、学習へのモチベーションを高めることができます。
特にM&Aのように実務での経験や知識が重要視される分野では、他の受講生とのネットワークが将来的に大きな財産となることもあります。専門学校や講座では、資格取得後のキャリアサポートが用意されている場合もあり、転職や実務経験の獲得を目指す際に役立つでしょう。
ただし、専門学校や講座の利用には高額な費用がかかることが多く、時間や場所に制約があるというデメリットもあります。
特に働きながら資格取得を目指す場合、通学が負担になることもあるでしょう。
したがって、講座の内容や費用対効果をしっかりと検討し、自分のスケジュールに合わせた学習方法を選ぶことが重要です。
オンライン学習
オンライン学習は、場所を選ばずに学習できるため、忙しい社会人や遠方に住んでいる人でも気軽に学習を始めることができる方法です。
通勤時間や自宅での空き時間を活用して学習を進められるため、時間を有効に使いたい人にとっては理想的な学習方法です。また、オンラインコースは録画された講義が多く、自分のペースで何度でも視聴できるので、苦手な部分を繰り返し学ぶことができます。
さらに、オンラインプラットフォームでは、最新の学習リソースが提供されていることが多く、リアルタイムでのオンラインセミナーやQ&Aセッションを通じて、講師と直接やり取りができるケースもあります。
これにより、実際の授業と変わらない質の高い教育を受けることができるだけでなく、他の受講生とバーチャルでつながり、情報交換やディスカッションを行うことも可能です。
一方で、オンライン学習のデメリットとしては、自己管理能力が求められる点が挙げられます。オンライン学習は自由度が高い反面、学習の進捗を自己管理しなければならず、計画的に学習を進めないと途中で挫折してしまうリスクもあります。
特に、M&A資格のように専門的で広範な知識が必要な場合、継続的に学習を進めるためのモチベーション維持が重要です。
そのため、オンライン学習を選ぶ際には、自分自身で学習計画を立て、進捗を管理するためのツールやリマインダーを活用すると良いでしょう。
M&A資格取得の費用と時間
M&A資格の取得には、学習時間と費用の両方が重要な要素となります。資格の種類によって必要な学習時間や費用は大きく異なり、国家資格と民間資格でその傾向は特に顕著です。
ここでは、M&A資格を取得する際にかかる時間とコストについて、国家資格と民間資格の両方の観点から解説します。
資格ごとの学習時間とコスト
ここからは、資格ごとの学習時間とコストについて具体的に解説していきましょう。
国家資格の学習にかかる時間と費用
M&Aに関連する国家資格(例えば、公認会計士、税理士、弁護士など)は、その専門性の高さから、非常に難易度が高いものが多いです。これらの資格を取得するには、試験範囲が広く、内容も非常に高度なため、学習にかかる時間は通常1年以上、場合によっては数年にわたることもあります。
例えば、公認会計士試験の合格には、一般的に2,000時間から3,000時間以上の学習が必要とされています。
また、税理士試験の場合は、複数科目を合格しなければならないため、5年以上かけて一つずつ科目をクリアしていく受験者も珍しくありません。
弁護士資格に至っては、法科大学院での勉強や予備試験の合格が必要であり、合格までの道のりは非常に長く、学習に費やす時間は膨大です。
費用の面でも、国家資格はかなりの負担がかかります。
たとえば、公認会計士試験の受験料は19,500円ですが、試験に合格するための専門学校や予備校の費用が数十万円から数百万円に達することも多いです。
税理士試験の科目別の受験料も数千円から1万円程度ですが、5科目すべてを合格するまでには数年かかるため、その間の学習費用や教材費などの総額はかなりのものになります。
弁護士資格に関しても、法科大学院の学費や予備校の費用を合わせると数百万円以上の投資が必要となる場合があります。
このように、国家資格を取得するためには、長期間の学習と高額なコストが必要です。そのため、事前にしっかりとした計画を立て、学習のスケジュールと予算を把握しておくことが重要です。
民間資格の学習にかかる時間と費用
一方、民間資格(M&Aスペシャリスト資格、JMAA認定M&Aアドバイザー、M&Aエキスパート認定資格、事業承継士など)は、国家資格に比べて比較的取得しやすく、学習にかかる時間や費用も抑えられるケースが多いです。
これらの資格は、M&Aの特定の分野や実務にフォーカスしており、実践的な知識を短期間で習得することができるのが特徴です。
たとえば、M&Aスペシャリスト資格は、講座を受講した後に試験を受ける形式で、学習期間は数ヶ月程度が目安とされています。
受講料は77,000円、試験料は11,000円で、総額88,000円と国家資格と比べてコストが抑えられています。
また、JMAA認定M&Aアドバイザーのように、受講と審査を経て資格を取得するタイプの場合、学習期間も数ヶ月で済むことが多く、受講料や月会費を含めた費用は年間で30万円程度となります。
M&Aエキスパート認定資格も、基礎的な試験から上位資格まで段階的に取得が可能で、費用も7,700円と手頃です。しかし、上位資格を目指す場合には、専用の養成スクールに通う必要があり、その費用や学習時間が追加でかかるため、資格の段階によって必要なコストが変わります。事業承継士資格に関しては、講座受講費用が300,000円、試験料9,000円などがかかり、受験するための条件として他の資格の取得が求められる場合もあるため、その点も考慮が必要です。
民間資格は、短期間での学習や集中講座などが利用できるため、スケジュール調整がしやすく、働きながら資格取得を目指す方に向いています。
しかし、各資格によって学習内容や対象分野が異なるため、取得する資格が自分のキャリアにどのように役立つのか、事前にしっかりと検討することが重要です。
国家資格と民間資格はそれぞれの特徴が異なり、必要な学習時間や費用も大きく異なります。
長期的に高い専門性を持ちたい場合は、国家資格に挑戦する価値がありますが、短期間で実務に直結するスキルを身につけたい場合は、民間資格を検討するのも良いでしょう。
資格取得を目指す際には、しっかりと時間と費用を見積もり、計画的に学習を進めることが成功の鍵となります。
本記事では、M&Aに必須の部署とその担当役割について解説します。経営企画部署、M&A統括部署、法務部署、経理(財務)部署…
まとめ: 自分のキャリアに合ったM&A資格を選ぼう
M&A業務において資格を取得することは、専門知識を証明し、信頼性を高める大きなメリットがあります。国家資格は難易度が高く、時間と費用がかかるものの、深い専門性を証明できます。
一方、民間資格は短期間で実務的なスキルを習得するのに向いています。
自分の目指すキャリアに合った資格を選び、計画的に学習を進めることで、M&Aの現場で活躍できる実力を身につけましょう。