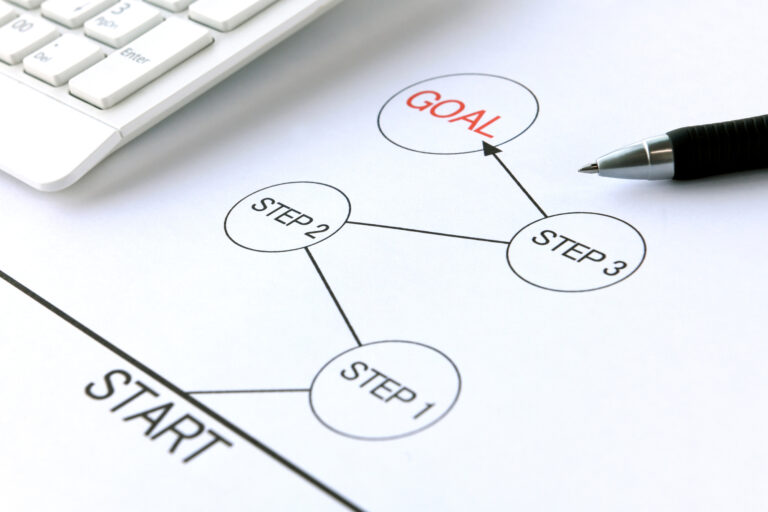M&Aは、企業成長や戦略的な経営目標の達成において、欠かせない手法の一つです。しかし、M&Aにはさまざまなスキーム(手法)が存在し、それぞれ異なる特徴や適用条件があります。スキーム選定は、M&Aの成否を左右する重要な要素であり、選択を誤れば意図しないリスクやコストが発生する可能性もあります。
本記事では、M&Aの全貌を掘り下げ、代表的なスキームの種類や特徴を解説するとともに、選択時に考慮すべきポイントを徹底的に解説します。企業が直面する課題や目標に最適なスキームを見極め、成功に導くための知識を提供します。
- この記事を監修した人:福住優(M&A情報館 代表取締役)
M&Aスキームの基本概念
企業が成長戦略や経営課題の解決策としてM&Aを検討する際、適切な「スキーム(手法)」を選ぶことが重要です。M&Aスキームは、取引の目的や条件、実現したい成果によって大きく異なり、その選択がM&A全体の成功を左右します。本節では、M&Aスキームの基本概念について解説し、スキームの持つ役割やその選択が経営に与える影響について説明します。
M&Aスキームとは?
M&Aスキームとは、企業が買収や合併を行う際に用いる具体的な取引手法を指します。この手法は、株式譲渡や事業譲渡、会社分割、合併など多岐にわたり、目的や状況に応じて選択されます。例えば、株式譲渡は迅速な経営権の移転が可能であり、事業譲渡は必要な資産や権利のみを選別して承継することが可能です。

各スキームには法的、税務的な要件があり、それぞれ異なるメリットやデメリットがあります。例えば、株式交換では現金を使わずに取引を実現できる一方、簿外債務のリスクが伴う場合もあります。一方、事業譲渡は選別的な承継が可能ですが、許認可の再取得や契約の再締結が必要となる場合があります。M&Aスキームを理解し、適切に活用することで、取引全体の効率性と成功率を向上させることができます。
スキーム選択の重要性
M&Aスキームの選択は、単に取引を完了させるための手段ではなく、企業がその後の経営戦略を実現するための重要な要素です。スキーム選択の適否は、税務的な負担、法務的なリスク、承継する権利や義務の範囲、取引の迅速性や効率性など、複数の観点で検討される必要があります。
例えば、売り手の立場であれば、株式譲渡による譲渡益を優先するか、あるいは事業譲渡を通じて不要な負債を切り離すかが重要な検討事項となります。一方で、買い手の立場では、買収コストの最小化やスムーズな統合を目指してスキームを選定することが求められます。
さらに、税制適格要件を満たすことで、課税の繰り延べや節税効果を得られる場合があります。そのため、スキーム選択の際には、税理士や弁護士といった専門家の助言を受けることが推奨されます。
スキームの分類と選定基準
M&Aスキームは、その目的や承継内容、対価の形態、法務・税務の条件によって分類されます。主なスキームとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 株式取得(株式譲渡、株式交換、株式移転、第三者割当増資):対象会社の経営権を迅速に掌握したい場合に選択される。
- 事業譲渡:特定の事業や資産のみを選別して引き継ぎたい場合に適している。
- 会社分割(吸収分割、新設分割):企業の一部門を独立させたり、事業の選択と集中を図る際に活用される。
- 合併(吸収合併、新設合併、三角合併):企業間の統合を目的とし、シナジー効果の最大化を図る。
- 資本提携・業務提携:出資や共同事業を通じて関係を強化し、戦略的な連携を図る。
選定基準としては、まず、買収や合併の目的を明確にすることが重要です。その目的が事業の拡大であれば、株式取得や合併が有力な選択肢となります。一方、特定の事業のみを獲得したい場合は事業譲渡や会社分割が適しています。また、税務上の優遇措置や法務的なリスク軽減を考慮し、適格性や法令遵守の観点から選定を進める必要があります。

適切なスキーム選択は、M&Aの成功に直結します。企業の現状や目標を詳細に分析し、各スキームの特性を踏まえて選択することが求められます。専門家の助言を活用しながら、慎重に検討することがM&A成功の鍵となるでしょう。
DawnX株式会社では、豊富な知見を活かし、最適なスキーム選定とプロセス全体のサポートを提供しています。ぜひご相談ください。
代表的なM&Aスキームの種類と特徴
M&Aは、企業の成長や競争力強化において非常に重要な手段ですが、その具体的な手法やスキームには多くの種類があります。それぞれのスキームは目的や状況に応じた特徴を持ち、適切に選択することで、企業価値を最大化することが可能です。本節では、代表的なM&Aスキームの種類と特徴について解説します。
合併(Merger)の特徴
合併は、複数の企業が統合して1つの会社となるスキームであり、M&Aにおける基本的な手法の1つです。合併には、既存企業が存続して他の企業を吸収する「吸収合併」と、新しい会社を設立して全ての合併企業が解散する「新設合併」の2つの形態があります。
合併の大きな特徴は、経営資源やノウハウ、人材などを包括的に承継できる点にあります。これにより、シナジー効果を生み出し、企業の競争力を向上させることが期待できます。ただし、統合には多大な時間とコストがかかるため、計画的かつ戦略的に進める必要があります。
吸収合併と新設合併の違い
吸収合併と新設合併の主な違いは、合併後の会社の存続形態です。
・吸収合併
吸収合併では、存続企業が合併後もそのまま存続し、消滅企業の権利義務をすべて引き継ぎます。この形態は、効率的かつ迅速に統合を進めることができるため、特に企業間の規模や経営状況に大きな違いがある場合に適しています。
・新設合併
新設合併は、合併に参加したすべての企業が解散し、新たに設立された企業に権利義務が引き継がれる形態です。この方法は、企業間の対等性を重視する場合や、新しいブランド戦略を展開したい場合に選ばれます。ただし、手続きが煩雑で時間がかかることがデメリットです。
合併によるシナジー効果とリスク
合併の主な目的は、シナジー効果を得ることです。シナジー効果には以下のような種類があります。
- 経済的シナジー:コスト削減や資源の効率的な利用
- 営業的シナジー:市場シェア拡大や顧客基盤の強化
- 技術的シナジー:新技術やノウハウの共有
一方で、合併にはリスクも伴います。統合プロセスがうまくいかない場合、企業文化の違いや人材の流出、期待した効果が得られないなどの課題が生じることがあります。また、簿外債務の引き継ぎや統合コストが想定以上にかかる場合もリスクとして考慮すべきです。
買収(Acquisition)の特徴
買収は、企業が他の企業を直接取得して支配権を獲得するスキームです。買収の特徴は、株式や事業の取得を通じて、短期間で経営権を確保できる点にあります。買収は、株式譲渡や事業譲渡をはじめ、さまざまな形態を取ることができます。
買収の目的には、事業拡大、新規市場への進出、競合他社の排除などがあります。特に、既存の経営資源を活用してシナジー効果を高めることや、新しい事業領域に迅速に参入するための手法として広く活用されています。
株式譲渡と事業譲渡の違い
株式譲渡では、対象企業の株式を取得することで、その企業全体を引き継ぐことが可能です。手続きが比較的簡便であり、迅速に経営権を確保できる一方、簿外債務や不要な資産も引き継ぐリスクがあります。
事業譲渡は、対象事業や資産を選択的に承継する方法です。この方法では、不要な債務や事業を引き継がずに済むため、リスクを最小限に抑えることが可能です。しかし、許認可や契約の再取得が必要となる場合があり、手続きが煩雑になることがあります。
どちらのスキームを選ぶべきかは、買収の目的やリスク許容度、税務上の条件などを総合的に検討する必要があります。
買収プロセスで注意すべき点
買収のプロセスは、成功の鍵となる重要なステップを含んでいます。以下のプロセスと注意点を把握することが必要です。
・デューデリジェンス(Due Diligence)
買収対象の財務状況や経営状況、法務リスクを徹底的に調査します。この段階での見落としが後のトラブルにつながるため、専門家を交えた慎重な分析が求められます。
・買収契約の締結
契約内容には、価格、条件、保証事項などが含まれます。不備があれば、後の交渉で問題が発生する可能性が高まります。
・クロージングと統合(Post Merger Integration, PMI)
クロージング後の統合プロセスでは、文化や業務システムの統合が課題となります。特に、企業文化の違いは統合の成功を左右する要素です。
会社分割(Company Split)の特徴
会社分割は、企業が事業部門を分離し、新たに設立する会社や既存の会社に承継させるスキームです。この方法は、事業再編や戦略的な資源配分を目的として行われます。
主な特徴は以下の通りです。
- 包括的な承継:会社分割では、権利義務が包括的に引き継がれるため、承継手続きが効率的です。
- 柔軟性:不要な事業を切り離し、特定の事業に資源を集中させることが可能です。
- スムーズな統合:分割された事業が他社に統合されることで、相乗効果が期待されます。
吸収分割と新設分割のメリット
会社分割には、吸収分割と新設分割の2種類がありますが、以下のように、それぞれ異なるメリットがあります。
・吸収分割
吸収分割とは、既存企業が分割された事業部門を承継する方法で、迅速な統合が可能です。分割元企業には現金を用意する必要がなく、分割後も経営に関与できます。
・新設分割
新設分割:新たに設立した企業に事業部門を承継する方法で、分社化による経営の効率化が目的です。この方法は、特定事業に特化した経営体制を整える場合に適しています。

経営戦略における会社分割の活用例
会社分割は、以下のような経営戦略で活用されます。
- 事業再編:赤字部門や非効率な事業を分離し、健全な経営基盤を構築する。
- 成長戦略:成長分野の事業を分割し、投資を集中させる。
- 資本提携:分割した事業を他社に譲渡することで、新たな協力関係を築く。
DawnX株式会社のエキスパートが、企業の成長目標に合わせた最適なスキーム選定をサポートし、リスクを最小限に抑えた戦略を実現します。
株式交換と株式移転の特徴
株式交換と株式移転は、親会社と子会社の関係を構築するための手法です。
・株式交換
対象企業の株式をすべて取得し、対価として親会社の株式を交付します。完全親子会社関係を構築するために利用されることが一般的です。
・株式移転
新設する持株会社に既存会社の株式を移転し、その対価として持株会社の株式を交付します。主にホールディングス体制を形成する際に活用されます。
完全親子会社化のプロセス
完全親子会社化では、親会社が子会社の全株式を保有する状態を目指します。これにより、経営方針を統一し、効率的な運営を実現します。プロセスでは、株主間の合意形成や適切な対価の設定が重要です。
株式交換と株式移転が適したケース
株式交換
迅速に完全子会社化を実現したい場合や、対価として株式を用いることで現金負担を回避したい場合に適しています。
株式移転
複数の企業を統合して持株会社を設立し、グループ全体のシナジー効果を高めたい場合に有効です。
新株引受(第三者割当増資)の特徴
第三者割当増資は、特定の第三者に新株を発行するスキームです。この方法は、資金調達や経営関係の強化を目的としています。
・迅速な資金調達
増資により資本を増強し、事業拡大や負債削減を進めることが可能です。
・経営権の変化
発行株式数に応じて、第三者が経営に影響を与える場合があります。
資金調達としての第三者割当増資の効果
第三者割当増資は、以下の効果を持ちます。
・財務基盤の強化
新たな資金を獲得し、事業成長の基盤を整備。
・戦略的パートナーシップ
株式を引き受けた企業との関係を深め、長期的な協力体制を構築。
成長企業での新株引受の活用事例
成長企業では、第三者割当増資が新規事業の展開や市場拡大に活用されています。具体例としては、テクノロジー分野でのベンチャー企業が、戦略的パートナーからの出資を受けて事業を拡大するケースが挙げられます。このようなスキームは、短期間での成長を実現するための有効な手段です。
M&Aの目的に応じたスキームの選択
M&Aを成功させるためには、目的に応じた適切なスキームを選択することが重要です。企業は、事業拡大、事業承継、シナジー効果の実現、コスト削減など、さまざまな目的でM&Aを実行します。
以下は、目的別の適したスキームの例です。
- 事業拡大を目的とする場合:株式譲渡や株式交換が適しています。既存事業に関連する企業を買収することで、迅速に市場シェアを拡大できます。
- 事業承継を目的とする場合:事業譲渡や会社分割が有効です。特に中小企業において、後継者不足の問題を解決しつつ、従業員や取引先との関係を維持できます。
- コスト削減を目的とする場合:吸収合併が選ばれることが多いです。複数の企業を統合することで、重複するコストを削減できます。
企業が目指すゴールに最も合致するスキームを選ぶことで、M&Aの効果を最大化することが可能です。
新規事業展開や事業承継に適した手法
新規事業展開や事業承継を目指す企業にとって、スキーム選定は戦略的な意味を持ちます。
1. 新規事業展開
・株式移転:ホールディングス体制を構築し、複数の事業を一元的に管理する場合に有効です。
・第三者割当増資:成長可能性の高い分野での新規事業に対し、資金を効率的に調達できます。
2. 事業承継
・事業譲渡:対象事業の特定資産や負債を選別し、効率的な承継を実現します。
・会社分割:承継対象を事業単位で分割し、事業承継や資本提携を進めやすくします。
これらのスキームは、それぞれの状況や目的に応じた柔軟な対応が可能であり、企業の成長や持続可能性を支える重要な手法となります。

財務面で考慮すべき要素
M&Aスキームの選定において、財務面の考慮は不可欠です。以下の点を検討することが推奨されます。
- 買収コストの管理:スキームに応じて、現金対価や株式対価などのコスト構造が異なります。これにより、企業の資金繰りや財務状況が影響を受けるため、慎重な検討が必要です。
- 資本構成の変化:第三者割当増資や株式交換では、資本構成が変化し、経営権に影響を及ぼす可能性があります。
- のれんの発生:事業譲渡や合併では、対象企業の資産価値を超える支払いが発生する場合、「のれん」として計上されます。こののれんの償却方法や影響を事前に理解しておくことが重要です。
財務的なリスクを最小限に抑えながら、スキームを選定することで、企業の安定性を維持できます。
負債の引き継ぎリスクと回避策
M&Aでは、買収対象企業の負債の引き継ぎリスクが避けられません。負債には、簿外債務や契約上の義務が含まれる場合があります。このリスクを管理するためには、以下の回避策が有効です。
- 事業譲渡を選択:事業譲渡は、引き継ぐ資産や負債を選択できるため、不要な負債を回避することが可能です。
- デューデリジェンスの強化:買収前に負債やリスクを詳細に調査し、不測の負担を回避します。
- 保証契約の設定:売り手企業に対し、特定の負債やリスクに関する保証を求めることで、リスクを軽減できます。
これらの手法を活用することで、負債引き継ぎのリスクをコントロールし、M&Aの安全性を向上させることが可能です。
法務と税務の視点でのスキーム選定
M&Aスキームを選ぶ際には、法務と税務の観点も重要な検討材料となります。
- 法務の視点:各スキームには、法的な承認手続きや契約要件があります。たとえば、合併では株主総会の特別決議が必要であり、事業譲渡では個別契約の再締結が求められる場合があります。
- 税務の視点:スキームごとに異なる税制が適用されます。適格組織再編に該当する場合、譲渡益課税を繰り延べられることがありますが、非適格組織再編では即時課税の対象となる可能性があります。
法務と税務のバランスを考慮したスキーム選定が、長期的な経営安定に寄与します。
デューデリジェンスで確認すべき項目
M&Aの成否を左右する重要なプロセスが、デューデリジェンス(Due Diligence)です。このプロセスでは、買収対象企業の財務状況、法務リスク、事業運営状況などを詳細に分析します。以下は、デューデリジェンスで特に注目すべき項目です。
1. 財務デューデリジェンス
・過去の財務諸表の分析:収益性やキャッシュフロー、財務健全性を評価します。
・負債状況:簿外債務や潜在的な負債リスクを洗い出します。
・資産の実態:資産価値の過大評価や不良資産の有無を確認します。
2. 法務デューデリジェンス
・許認可や契約の確認:重要な許認可や取引契約の継続性を確認します。
・訴訟リスク:未解決の訴訟や法的問題の有無を精査します。
・知的財産権の状況:特許、商標、著作権の保有状況や関連するリスクを確認します。
3. 事業デューデリジェンス
・市場ポジション:競争環境や市場シェアを評価します。
・顧客基盤:主要顧客との関係性や契約の安定性を分析します。
・業務運営:事業運営の効率性や従業員の状況を調査します。
デューデリジェンスを徹底することで、潜在的なリスクを把握し、適切なM&A戦略を策定できるでしょう。
DawnX株式会社は、財務、法務、事業面での徹底的なデューデリジェンスを支援し、潜在リスクを洗い出すことで、安心してM&Aを進められる環境を提供します。
税制適格要件を活用した節税効果
M&Aスキームの選定において、税制適格要件を活用することは、節税効果を高める重要な手法です。税制適格要件を満たす場合、一定の条件下で譲渡益課税を繰り延べることが可能です。
適格組織再編の条件
・継続性要件:再編後も事業が継続していること。
・支配要件:特定の支配関係が継続していること。
・経済合理性要件:単なる税務上のメリットを目的としないこと。
具体的な節税効果
・株式交換や株式移転:税制適格要件を満たす場合、譲渡益課税が繰り延べられるため、即時の現金負担が軽減されます。
・合併や会社分割:適格要件を満たせば、資産や負債が簿価で承継され、含み益に対する課税を回避できます。
適用時の注意点
適格組織再編を目指す際には、事前に税務当局への確認や専門家の助言を求めることが重要です。要件を満たさない場合、予期しない課税が発生するリスクがあります。
税制適格要件を効果的に活用することで、M&A後の財務負担を軽減し、事業の安定した成長を支援することが可能です。
まとめ: スキームの選択がM&Aの鍵
M&Aのスキーム選択は、企業の戦略的な意思決定において極めて重要です。スキームごとに異なる特徴やメリット・デメリットがあり、目的に応じた適切な選択が、M&Aの成功を左右します。新規事業展開や事業承継といった目的に合わせてスキームを選び、財務・法務・税務の各視点からリスクやコストを最小限に抑えることが求められます。また、デューデリジェンスを通じて潜在的なリスクを把握し、税制適格要件を活用した節税効果を検討することで、経済的な負担を軽減することも可能です。
M&Aの成功には、スキームの詳細を深く理解し、自社の状況に合った手法を選択することが不可欠です。専門家の助言を活用しながら、慎重かつ戦略的にスキームを選び、長期的な経営の安定と成長を実現しましょう。